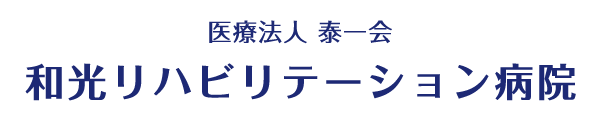理念
院長挨拶

院長 今村 健太郎
和光リハビリテーション病院は、2018年4月の開院以来、患者さんがご自宅で生き生きと日常生活を送るために私たちに出来ることを考え、邁進してまいりました。
この病院は、私が一から携わり、タイル一枚に至るまでこだわり抜いて建設したものです。
患者さんだけでなく、働くスタッフも気持ちよく働けるような環境づくりを心掛け、私の医師としての経験と、現場のスタッフたちの声を大切にし、患者さんがリハビリテーションに集中できる空間を創出できたと思っております。
立ち上げ後も、患者さんやスタッフからのフィードバックを真摯に受け止め、より良い病院を目指して日々改善を重ねてまいりました。
私たちの大きな役割の一つは、「元の暮らしへ戻れる」という前向きな気持ちを呼び起こし、患者さんを支えることです。
そのためには、患者さんの生活を想像し、自分なりの考えを持ちながら、患者さん一人ひとりと向き合っていくことが大切だと考えております。
多職種が連携し、患者さんの「暮らしがい」の実現をサポートすることで、患者さんの日々の笑顔に繋がれば幸いです。
当院のスタッフは自ら介護予防教室を行うなど、積極的に地域に関わっていく信頼できる仲間たちです。
今後もスタッフ一同、日々研鑽を積み、この地域に必要とされる病院であり続けるために努力してまいります。
院長
今村 健太郎 (IMAMURA Kentaro)
山梨県出身。杏林大学医学部卒。
心臓血管外科で多くの手術を行う中、手術後のリハビリテーションの重要さを感じ、整形外科に興味を持つ。
整形外科の手術も行いながら身体の機能回復の知見を深め、リハビリテーション科専門医を取得。
その実績から和光市に回復期リハビリテーション病院を建設する際に声が掛かり、「暮らしがい」へ繋がる病院作りを目指し日々研鑽を積んでいる。
所持資格/所属学会
- 日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医
- 日本外科学会 認定外科専門医
- ステントグラフト指導医
- 日本整形外科学会
- 日本血管外科学会
病院概要
- 名称
-
医療法人泰一会
和光リハビリテーション病院 - よみ
-
いりょうほうじん たいいちかい
わこうりはびりてーしょんびょういん - 開設
- 平成30年(西暦2018年)4月
- 所在地
-
〒351-0113
埼玉県和光市中央2-6-75 - 電話
- 048-464-6111(代表)
- FAX
- 048-464-6112
- 診療科目
- 内科/整形外科/脳神経外科/リハビリテーション科/放射線科
- 病床数
- 回復期リハビリテーション病棟: 79床
- 各種指定
-
- 保険医療機関
- 労災保険指定医療機関
- 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
- 施設基準
-
基本診療料
-
[医療DX]
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算とは?
医療DX推進体制整備加算とは、病院や診療所がデジタル化(DX)を進めるための取り組みを評価し、診療報酬として加算する制度です。患者さんにとってより良い医療を提供するために、医療機関が積極的にICT(情報通信技術)を活用することを促進することを目的としています。
どんなことをするの?
この加算を取得するためには、医療機関は様々な要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
- オンライン資格確認システムを導入していること
- 電子カルテシステムを導入していること
- 医療DXに関する具体的な計画を策定し、実行していること
医療DXに関する具体的な計画には、例えば以下のようなものが含まれます。
- オンライン資格確認の積極的な活用
(例:マイナンバーカードの普及促進) - 電子カルテシステムの機能拡充
(例:検査結果や画像データの共有、オンライン診療システムとの連携) - データ活用による医療の質の向上
(例:診療データの分析による業務効率化や治療効果の向上) - セキュリティ対策の強化
(例:患者情報の適切な管理)
患者さんにとってのメリットは?
医療DXが進むことで、患者さんには以下のようなメリットがあります。
- 待ち時間の短縮:オンライン資格確認や電子カルテの導入により、受付や会計がスムーズになります。
- 医療の質の向上:データ活用により、より適切な診断や治療を受けることができます。
- 利便性の向上:オンライン診療や検査結果のオンライン閲覧など、より便利なサービスを利用できるようになります。
加算の金額は?
この加算は、初診料や再診料などに上乗せされる形で加算されます。金額は医療機関の規模や取り組み内容によって異なります。
医療DX推進体制整備加算は、患者さんにとってより良い医療を提供するために重要な制度です。医療機関が積極的にデジタル化に取り組むことで、医療の質の向上、待ち時間の短縮、利便性の向上など、様々なメリットが期待されます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[データ提]
データ提出加算
データ提出加算とは?
データ提出加算とは、医療機関が質の高い医療を提供するために、診療に関するデータを集計・分析し、国に提出することを評価する制度です。このデータ提出によって加算される診療報酬のことを指します。簡単に言うと、医療の質の向上への取り組みを評価する加算です。
なぜデータ提出が必要なの?
医療の質を向上させるためには、現状を把握し、改善策を講じる必要があります。そのためには、全国の医療機関から様々なデータを収集し、分析することが不可欠です。集められたデータは、医療政策の立案や医療技術の向上に役立てられます。また、患者さんにとっても、質の高い医療機関選びの参考情報となります。
データ提出加算の種類と内容
データ提出加算には様々な種類があり、提出するデータの内容や対象となる医療機関が異なります。例えば、以下のようなものがあります。
- がん登録:がんと診断された患者さんの情報を登録し、がん対策に活用します。
- DPCデータ提出:診断群分類(DPC)と呼ばれる方法で患者さんの病状を分類し、医療費や在院日数などを分析します。病院の経営効率や医療の質の評価に用いられます。
- 診療報酬明細書データ提出:診療報酬の請求内容を詳しく分析し、医療費の適正化や医療の質の向上に活用します。
- 臨床指標データ提出:手術や検査、治療などの結果に関するデータを提出し、医療の質の評価や改善に役立てます。例えば、手術後の合併症発生率や感染症発生率などが含まれます。
データ提出加算を受けるには?
データ提出加算を受けるためには、それぞれの加算で定められた基準を満たす必要があります。具体的には、
- 指定されたデータ項目を正確に収集・登録すること
- 決められた期限までに国に提出すること
- データの質を確保するための体制を整備すること
などが求められます。これらの基準を満たすことで、医療機関はデータ提出加算を受けることができます。
私たち患者にとってのメリット
医療機関がデータ提出加算に取り組むことで、医療の質の向上や医療費の適正化が期待できます。これは、患者さんにとって、より良い医療サービスを受けられることに繋がります。また、公開されているデータは、医療機関を選ぶ際の参考情報として活用することもできます。
ただし、データ提出加算は、医療費が上がることを意味するものではありません。加算によって得られた診療報酬は、データ収集・分析にかかる費用や、医療の質の向上のための取り組みに活用されます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[回1]
回復期リハビリテーション病棟入院料1
回復期リハビリテーション病棟入院料1とは?
「回復期リハビリテーション病棟入院料1」は、脳卒中や骨折など、病気やケガで身体機能が低下した方が、集中的なリハビリテーションを受けてスムーズに家庭や社会復帰を目指すための、特別な医療サービスに対する費用です。この費用は、入院中に病院が提供する様々なサービスを包括したもので、医療保険から支払われます。
対象となる方
この入院料の対象となる方は、主に以下のような状態の方です。
- 脳血管疾患(脳卒中など)
- 大腿骨頸部・転子部・転子下骨折
- 脊髄損傷
- 頭部外傷
など、一定の基準を満たす状態にある方
どんなサービスが含まれる?
この入院料には、以下のようなサービスが含まれています。
- リハビリテーション:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによる、身体機能の回復を目的とした訓練
- 看護:日常生活の介助や医療処置など
- 食事:栄養バランスの取れた食事の提供
- 投薬・注射:医師の指示に基づいた薬の投与
- 検査:状態の確認や治療効果の判定のための検査
「1」って何?
回復期リハビリテーション病棟入院料には、提供されるリハビリテーションの量や質に応じて、「1」から「5」までの段階があります。「1」は、比較的軽度の状態の方を対象としており、1日あたり3時間以上(週に6日以上)のリハビリテーションを提供します。数字が大きくなるほど、より重度の状態の方を対象とし、リハビリテーションの提供時間も長くなります。
費用について
費用は、患者の状態や医療機関によって異なりますが、医療保険が適用されます。自己負担額は、加入している保険の種類や所得によって異なります。詳しくは、入院先の医療機関にお問い合わせください。
まとめ
回復期リハビリテーション病棟入院料1は、身体機能の回復と社会復帰を目指す上で重要な役割を果たす入院料です。専門スタッフによる集中的なリハビリテーションを受けることで、日常生活の自立度を高め、より良い生活を取り戻すことを目指します。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
特掲診療料
-
[二骨継2]
二次性骨折予防継続管理料2
二次性骨折予防継続管理料2とは?
骨粗鬆症による骨折は、一度起こると再び骨折するリスクが非常に高くなります。これを「二次性骨折」と言います。二次性骨折を防ぐための継続的な管理に対して支払われる診療報酬が「二次性骨折予防継続管理料2」です。簡単に言うと、骨折を経験した人が再び骨折しないように、病院で継続的にサポートを受けるための費用です。
対象となる方
この診療料の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。
- 過去に骨粗鬆症による骨折を経験した方
(大腿骨近位部、脊椎、橈骨遠位端など) - 再び骨折するリスクが高いと医師が判断した方
どのような管理が行われるのか?
この診療料には、以下の内容が含まれています。
- 骨折リスクの評価:骨密度検査などを行い、骨折リスクを定期的に評価します。
- 生活指導:栄養指導や運動指導など、生活習慣の改善をサポートします。
- 薬物療法の管理:骨粗鬆症の治療薬を適切に服用するための指導や管理を行います。
- 骨折予防のための指導:転倒予防のための対策など、骨折を防ぐための具体的な指導を行います。
- 他の医療機関との連携:必要に応じて、他の医療機関と連携して治療を進めます。
費用は?
この診療料は、医療機関によって多少異なりますが、3ヶ月ごとにかかります。受診のたびに支払うのではなく、3ヶ月間の管理に対してまとめて費用が発生するイメージです。具体的な金額は医療機関にお問い合わせください。
まとめ
「二次性骨折予防継続管理料2」は、骨粗鬆症による骨折を経験した方が、再び骨折するリスクを減らし、健康な生活を送れるようにサポートするための重要な診療料です。骨折後の適切な管理は、生活の質の向上に大きく貢献します。該当する方は、ぜひ医師に相談してみてください。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 - 過去に骨粗鬆症による骨折を経験した方
-
[脳Ⅰ]
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)とは?
脳卒中(脳梗塞、脳出血など)や頭部外傷などで、身体に麻痺などの後遺症が残ってしまった方に対して、集中的なリハビリテーションを提供するための医療サービスです。このリハビリテーションは、病院やクリニックなどで、医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門スタッフによって行われます。この「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」は、質の高いリハビリテーションを提供するための基準を満たした医療機関に対して、国から認められた特別な診療報酬です。
どんなリハビリテーションを受けられるの?
「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」を取得している医療機関では、患者さん一人ひとりの状態に合わせた、より専門的で充実したリハビリテーションを提供しています。具体的には以下のような内容が考えられます。
- 日常生活動作の訓練:食事、着替え、トイレ、入浴など、日常生活で必要な動作の練習を行います。
- 歩行訓練:杖や歩行器を使って安全に歩けるように練習したり、バランス能力を高める訓練を行います。
- 麻痺した手足の機能回復訓練:麻痺した手足の筋力や動きを改善するための訓練を行います。
- 言語訓練:言葉がうまく話せない、理解できないといった症状に対して、コミュニケーション能力を高める訓練を行います。
- 嚥下(えんげ)訓練:食べ物を飲み込みづらくなった方に対して、安全に食事ができるように訓練を行います。
この基準を満たす医療機関の特徴
「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」の施設基準を満たしている医療機関は、以下のような特徴があります。
- チーム医療の提供:医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、多職種の専門スタッフが連携してリハビリテーションを提供しています。
- 一定時間以上のリハビリテーション提供:患者さんの状態に合わせて、必要な時間のリハビリテーションを提供しています。
- 適切なリハビリテーション計画の作成:患者さんの目標や生活状況などを考慮し、個別のリハビリテーション計画を作成しています。
- 定期的な評価と見直し:リハビリテーションの効果を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直しています。
つまり、「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」を取得している医療機関は、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供できる体制が整っていると言えるでしょう。脳卒中などの後遺症でお困りの方は、この基準を満たした医療機関を探してみると良いでしょう。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[運Ⅰ]
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?
「運動器リハビリテーション料(Ⅰ)」とは、関節や筋肉、骨などに問題を抱え、日常生活に支障が出ている方に対して、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供するための診療報酬です。整形外科やリハビリテーション科などで算定されるもので、この基準を満たした医療機関では、より充実したリハビリを受けることができます。
対象となる方
主に、骨折や関節の手術後、変形性関節症、腰痛、肩こり、スポーツ障害など、運動器の機能に問題があり、日常生活動作(歩く、立つ、座る、着替えるなど)に支障が出ている方が対象となります。
どのようなリハビリテーションが受けられるの?
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定している医療機関では、医師や理学療法士、作業療法士など、複数の専門家が連携して、患者さん一人ひとりに合わせたリハビリテーションプログラムを作成・実施します。
- 個別的な評価: 現在の身体の状態や日常生活での困りごとなどを詳しく評価します。
- 目標設定: 患者さんと一緒に、リハビリテーションを通して達成したい目標を設定します。例えば、「一人で歩けるようになる」「階段の上り下りが楽になる」などです。
- 計画的なリハビリテーションの実施: 設定した目標に基づいて、運動療法、物理療法(温熱療法、電気療法など)、装具療法などを組み合わせて、計画的にリハビリテーションを実施します。
- 定期的な評価とプログラムの見直し: リハビリテーションの効果を定期的に評価し、必要に応じてプログラムの内容を見直します。
- 日常生活への指導: 家庭での運動方法や日常生活動作の工夫などを指導し、リハビリテーションの効果を維持・向上させます。
この基準を満たす医療機関の特徴
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するためには、厚生労働省が定めた一定の基準を満たす必要があります。具体的には、
- 適切な人員配置:一定数以上の医師、理学療法士、作業療法士などを配置している。
- 設備基準:必要なリハビリテーション機器や設備を備えている。
- 質の高いリハビリテーションの提供: 研修会などに参加し、常に最新の知識や技術を習得するよう努めている。
などが求められます。そのため、この基準を満たした医療機関では、より専門的で質の高いリハビリテーションを受けることができると言えます。
より詳しい内容については、かかりつけの医師や医療機関にお問い合わせください。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[集コ]
集団コミュニケーション療法料
集団コミュニケーション療法料とは?
集団コミュニケーション療法料とは、精神科病院や診療所などで、複数の人々が集まって行うコミュニケーションの練習に対して支払われる医療費のことです。この療法は、対人関係の困難や社会生活への適応に問題を抱える方を対象としています。
目的
集団コミュニケーション療法の目的は、患者さんが安全な環境で他の患者さんと交流しながら、コミュニケーション能力を高めることです。具体的には、以下のような効果が期待されます。
- 対人関係のスキル向上(例:相手の話を聞く、自分の気持ちを伝える)
- 社会への適応能力の向上(例:職場や学校でのコミュニケーション)
- 自己肯定感の向上
- 孤立感の軽減
- 症状の改善(例:不安、抑うつ)
どのような人が対象?
以下のような症状や困難を抱える方が対象となります。
- 統合失調症
- 気分障害(うつ病、双極性障害など)
- 不安障害(社交不安障害、パニック障害など)
- 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHDなど)
- パーソナリティ障害
- 認知症
- その他、対人関係や社会生活に困難を抱えている方
療法の内容
集団コミュニケーション療法では、少人数のグループで、決められたテーマに沿って話し合ったり、ロールプレイを行ったりします。訓練を受けた専門スタッフ(医師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士など)が進行役を務め、参加者の発言を促したり、適切なフィードバックを提供したりします。
療法の内容は、参加者の状態や目的に合わせて調整されます。例えば、以下のようなプログラムがあります。
- 自己紹介や他者理解を深める練習
- 感情の表現やコントロールの練習
- アサーティブなコミュニケーション(自分の意見を適切に伝える)の練習
- 問題解決能力のトレーニング
費用
集団コミュニケーション療法料は、健康保険が適用されます。費用は、医療機関や実施内容によって異なりますが、3割負担の場合、数百円程度です。
集団コミュニケーション療法は、対人関係や社会生活に困難を感じている方にとって、有効な治療法の一つです。気になる方は、主治医や医療機関のスタッフにご相談ください。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[外在ベⅠ]
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とは?
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、医療機関が質の高い医療を提供していることを評価する制度の一つです。厚生労働省が定めた一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される特掲診療料です。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。
どんな医療機関が対象?
病院や診療所など、外来診療や在宅医療を提供している医療機関が対象となります。ただし、この評価料を受け取るためには、厚生労働省が定めた様々な基準をクリアする必要があります。
どんな基準があるの?
主な基準は以下の通りです。大きく分けて、「質の高い医療の提供体制」と「多職種連携の推進」に関する基準があります。
- 質の高い医療の提供体制
- 医療の質の向上に向けた取り組み(PDCAサイクルの実施など)
- 医療安全対策の実施
- 感染症対策の実施
- 在宅医療の充実
- 多職種連携の推進
- 医師、看護師、薬剤師、その他医療スタッフ間での連携強化
- 地域包括ケアシステムへの貢献
- 他医療機関との連携
この評価料で何が変わるの?
この評価料を取得した医療機関は、より質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。
- より安全で安心な医療を受けられる
- 多職種によるチーム医療を受けられる
- 地域全体で質の高い医療を受けられることに繋がる
つまり、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を取得している医療機関は、患者さんにとってより良い医療を提供するために積極的に取り組んでいる証と言えるでしょう。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 - 質の高い医療の提供体制
-
[入ベ41]
入院ベースアップ評価料(1~165)
入院ベースアップ評価料とは?
入院ベースアップ評価料とは、病院の入院医療の質の向上を目的とした診療報酬制度の一つです。病院が一定の基準を満たすと、この評価料を算定することができます。つまり、より質の高い入院医療を提供している病院に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。
なぜ必要なの?
医療技術の進歩や高齢化の進展に伴い、入院医療にはより高度で専門的な対応が求められています。入院ベースアップ評価料は、病院が質の高い医療を提供するための努力を評価し、より良い医療環境の整備を促進するために設けられています。
評価のポイント
入院ベースアップ評価料には、1から165までの様々な種類があり、それぞれ特定の医療行為や体制に関する評価項目が設定されています。例えば、看護師の配置人数、医師の勤務体制、医療機器の整備状況、感染対策の実施状況などが評価の対象となります。病院はこれらの項目について基準を満たすことで、該当する評価料を算定することができます。
具体例
- 7対1入院基本料:7人の患者に対して1人以上の看護師を配置している場合に算定できる評価料です。看護師の配置人数が多いほど、手厚い看護を提供できるため、患者さんにとってより安全で安心な入院生活を送ることができます。
- 重症者等療養環境特別加算:集中治療室(ICU)など、重症患者に対応するための設備や人員を充実させている場合に算定できる評価料です。高度な医療を提供できる体制が整っていることを示しています。
- 入院時支援加算:入院患者の退院支援や在宅復帰に向けた取り組みを行っている場合に算定できる評価料です。スムーズな退院と、退院後の生活の質の向上に貢献します。
私たちにとってのメリット
入院ベースアップ評価料を算定している病院は、質の高い入院医療を提供している可能性が高いと言えます。病院を選ぶ際の参考情報の一つとして、これらの評価料の有無を確認してみるのも良いでしょう。ただし、評価料の種類が多いため、それぞれの意味を理解するのは難しいかもしれません。気になる評価料があれば、病院のスタッフに尋ねてみることをお勧めします。
最終的には、評価料の有無だけでなく、医師や看護師とのコミュニケーション、病院の雰囲気なども考慮して、自分に合った病院を選ぶことが大切です。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
その他
-
[酸単]
酸素の購入価格の届出
酸素の購入価格の届出とは?
医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。
なぜ届出が必要なの?
酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。
誰が、いつ届出するの?
酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。
届出しないとどうなるの?
届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。
私たちへの影響は?
この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。
まとめ
- 酸素の購入価格の届出は、医療機関が酸素の購入価格を国に報告する制度
- 医療費の適正化を図るための重要な仕組み
- 医療機関は毎年1回届出が必要
- 患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に貢献
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 -
[食]
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)とは?
入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。
これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。
食事療養(Ⅰ)とは
食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。
- 患者さんの病状に合わせた食事を提供
(糖尿病食、腎臓病食など) - 食事内容や栄養について相談できる体制の確保
- 嗜好や食べやすさを考慮した食事の提供
- 定期的な栄養状態の評価
生活療養(Ⅰ)とは
生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。
- 入院生活における相談窓口の設置
- 療養生活上の助言や指導
- 社会福祉士等による相談支援
- アメニティグッズの提供や快適な療養環境の整備
つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。
本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。 - 患者さんの病状に合わせた食事を提供
-
[医療DX]
医療DX推進体制整備加算
- 関連施設